- 2019-4-17
- 明治期【個別記事】
- 2 comments

日本の「資本主義の父」と言われる渋沢栄一の人となりから学ぶこと
新紙幣の発表が平成31年(2019年)4月9日に、麻生財務大臣から発表された。新しい一万円札に選ばれたのは、明治の経済人、渋沢栄一である。渋沢栄一は日本の「資本主義の父」と言われるが、その功績は経済にとどまらない。論語を深く学んだ渋沢栄一は、哲学者でもあった。現在も学ぶことの多い渋沢栄一についてまとめてみた。是非、ご覧を。
1.新一万円札 渋沢栄一!
新一万円札に選ばれたのは、渋沢栄一であった。発効されるのは5年後の「令和5年」となる2024年の予定なので、少し先ではある。しかし、この人選には「令和」と同様、私にとっては非常に喜ばしい結果だった。デザインについては少し異論があるが・・・。
「日本資本主義の父」と呼ばれ日本の経済の近代化に著しく貢献したのが渋沢栄一である。渋沢栄一が生まれたのは天保11年(1840年)で伊藤博文公(1841年生まれ)とほぼ同じ年である。幕末維新の志士といってもいい時代の渋沢ではあるが、では、西欧から学んで西欧化を進めたかというと全く違う。その考えは「論語」を大きな柱として、日本の伝統に基づいた考えであり、その上での経済の近代化を進めた。渋沢氏の「国富論」で、自分は当時から見ても甚だ「時代遅れ」とまで言っている。
まずは、渋沢栄一氏の言葉を見てほしい。
夢なき者は理想なし 理想なき者は信念なし
信念なき者は計画なし 計画なき者は実行なし
実行なき者は成果なし 成果なき者は幸福なし
ゆえに幸福を求むる者は夢なかるべからず。一人ひとりに天の使命があり、その天命を楽しんで生きることが、処世上の第一要件である
この言葉を見ただけでも、渋沢栄一の人となりが見て取れると思う。決して、商売を単なる「金集め」とは考えず、そこに「倫理」あるいは「道徳」がなければいけないと説いた人であった。
2.渋沢栄一の歩み
ページ目次 [ 開く ]
渋沢栄一氏は、天保11年(1840年)生まれで、昭和6年(1931年)まで生きた人で、当時では異例の91歳まで生きた人であった。

埼玉で生まれ、農家ではあるが手広く事業を展開する家に生まれた。父親の影響により若い頃から学に努め、特に漢学(China(中国)の学問)に通じた。渋沢の生まれたのが1840年でペリーの来航が1853年であるから、それからの激動の明治維新には十分に関わっていた。
もともとはいわゆる「尊皇攘夷(そんのうじょうい)」派で江戸幕府の倒幕に燃えた若い頃を過ごしていた。過激派の一人だったとも言える。しかし、最後の将軍となる徳川慶喜(よしのぶ)に接した後に、徳川幕府の幕臣として働くこととなる。その後、徳川幕府が倒れた後には、明治政府に使えることとなり、大蔵省の官僚として活躍した。
しかし、明治政府に仕えると言ってもそれを自分の天分とは思えず、「明治6年政変」の時に当時の大蔵大臣、井上馨(かおる)と共に明治政府を去る。その後は、実業家として活躍をし、特に銀行業を手広く進めた。
今の「みずほ銀行」の母体の一つである当時の「第一国立銀行(後の「第一勧銀」)の頭取となりそれを大きくしたことが渋沢の出発点である。その後、設立に関与した企業には枚挙にいとまが無い。東京瓦斯・東京海上火災保険・王子製紙・東京証券取引所・麒麟麦酒(現:キリンビール)・サッポロビール・東洋紡績(現:東洋紡)など、今の日本を支える企業を育てたのが、渋沢栄一氏である。まさに、「近代日本の経済の父」と言われる理由はここにある。これだけの企業を、銀行業を通じて大きく奨励し、発展させた。
そしてその活躍は実業界だけにとどまらない。「国家感」を持って実業を行っていた渋沢氏にとって、教育は大きなテーマであったので「日本女子大学校」(現在の日本女子大)や商法講習所(現在の一橋大学)の設立にも関わっている。
また一方で、経済の発展に伴う貧富の格差を心配した渋沢は、孤児院や養育院などを運用する団体に寄付するなど、社会事業にも情熱を注いだ人である。
3.論語と渋沢栄一 ~渋沢栄一の哲学~
ページ目次 [ 開く ]
これだけ書くと渋沢栄一は、「頭のいい人」といった印象や、「学者肌で経済成長を考える堅物」といった印象があると思う。しかし頭がいいだけではなく、渋沢栄一氏は非常に気さくで、人なつっこく、明るい性格であった。著書の「国富論」でのエピソードにはそれに事欠かない。当時から「お金中心主義」になっていく日本を心配した「悲観論」があったが、渋沢氏はそれではだめだと論じていた。「悲観」でもなく「楽観」でもなく「達観」しながら、時代を明るく見なければ未来は開けないと、努めて未来を明るく考えていた。個人的にはこのあたりが、私自身の考えと同じで、非常に同調するところである。
そして著書の代表が渋沢氏の「論語と算盤(そろばん)」である。まさにタイトルにあるとおり、渋沢氏が最も影響を受けそれを信じて活動した源泉が「論語」である。
「論語」は確かに生まれはChina(中国)大陸であり、そういう意味では「China(中国)のもの」とも言える。しかし、紀元前500年頃の孔子に広まり始めた論語とその教えは、大陸では勉強材料とならなかった。China(中国)大陸の歴史を見ればそれは歴然としている。そして、その代わりに日本人が最も「論語」を活用していると言われている。日本人は大陸からの知識を自分流にアレンジしつつ受けいれて、その考えを自分流に解釈しながら道徳の柱の一つとしてきた。この当時の日本の知識層は外国の教育にも耳を傾け、近代化へ向けて独自に進めていった。
渋沢栄一は論語という大陸の古典の考え方を日本式に取り入れた上で、実業あるいは労働には「倫理」が重要であり、金を儲けるだけが実業の目的であってはならない、と断じている。とにかく、実業あるいは労働についてその目的が重要とし、その目的とは決して個人の金儲けではなく、家族・地域や国といった「公益」を重んじなければいけないとしている。
あるエピソードがある。「私利(しり)」と「公益」のどちらを優先すべきか、という質問を渋沢氏に投げかけた実業家がいた。その答えはどんなだろう、と予測しながら見ていた。おそらく、「両者のバランスが重要」といった答えと思っていたが、違った。
というのが渋沢栄一の考えであった。渋沢氏は「私利」と「公益」を明確に定義した上で両者を求めることが、経営や実業と説いた。
常に国であり地域を重視し、経営とはその発展を目的とし未来を明るくするための物と信念を持って説き続けた人である。経済の人ではあるが、情熱と信念を持った「国士」であった。
4.渋沢栄一の名言
ページ目次 [ 開く ]
渋沢栄一氏の名言はいくつもある。渋沢栄一氏ほどではないが、私も同じく論語を勉強する者として、非常に勉強になる言葉が多い。いくつか挙げてみたい。
・自分が手にする富が増えれば増えるほど、社会の助力を受けているのだから、その恩恵に報いるため、できるかぎり社会のために助力しなければならない。
・心を穏やかにさせるには思いやりを持つことが大事である。一切の私心をはさまずに物事にあたり、人に接するならば、心は穏やかで余裕を持つことができるのだ。
・真の富とは道徳に基づくものでなければ決して永くは続かない。
今も全く色褪せない言葉の数々と思う。他にもいろいろあるので、興味のある方は是非ご覧を。渋沢栄一という人の人となりと、志の高さがうかがえる。また、現在を生きる上でもそのまま参考にできる考え方である。
5.渋沢栄一を見て現在を思う
ページ目次 [ 開く ]
新一万円札となる渋沢栄一氏は、名前だけは聞くがなかなかその実績や考え方は広まっていない。明治維新の志士の一人といってもいい人なのだが、どうしても「経営の人」といった印象で、ともすれば単なる実業家としてしか捉えられない面がある。
そんな人が一万円札として選ばれたことは、本当に嬉しく思う。ただ、あのデザインには賛同しかねるが・・・。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。





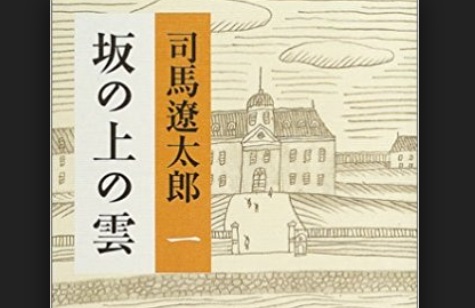






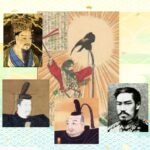







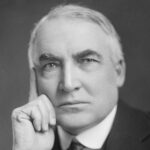
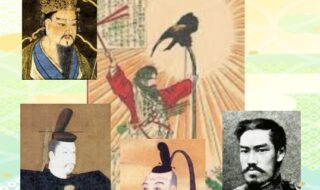
渋沢栄一はについては、実業家の面しか知らなかったのですが、人となりを知ると確かに1万円札に相応しい人物なんですね。
コンプライアンス教育よりも、こういった哲学に帰ることが今のビジネスマンに必要かも知れませんね。
ほんとにそうだね。日本人の先人たちの本当の姿を知ると誇りがもてろのと、身が引き締まります。
細かいコンプライアンスより、大きな理念っす!