- 2019-3-7
- 日々の思料
- 4 comments

梅の歴史と愛知県の大縣(おおあがた)神社の梅を見て思う
私は特別に花が好きなわけではなく、むしろ一般的な男性と同様に、花には大した興味は持っていない。しかし、「桜」だけは好きで毎年桜の開花の頃には必ず見るようにしている。そんな中で近年は、年を取ったせいか、「梅」を見て桜とは違った魅力を感じるようになった。梅について考えてみた。どうぞ、お付き合いを。
ページ目次
1.梅の魅力
桜に比べると梅は少し地味な印象がある。桜のように「ぱぁっと」咲くわけではなく、しっとりと力強い実と花を咲かせる。桜に比べて「派手さ」はない。開花の時期は桜の前で、大体2月頃が全盛で3月上旬くらいまでが、開花の時期となる。
梅を見ると、「もうすぐ桜が咲くな」とか「春は近いな」と本能的に思わせる。
今では圧倒的に桜の方が有名であり、日本人としての意識は桜が強い。しかし飛鳥時代・奈良時代には、花と言えば梅であったようである。日本人に深く根付く桜よりも、古代の日本人には梅が象徴だった。
2.梅を愛した日本人
ページ目次 [ 開く ]
このように桜に主導権を奪われた形の「梅」だが、そうはいっても梅を愛する日本人の心は大きくは変わっていない。歴史的に代表的な人を3人挙げてみた。
(1) 学問の神様 菅原道真(すがわらのみちざね)
菅原道真(すがわらのみちざね)公は、平安時代に活躍した政治家であり、学者であり、詩人であった人である。「学問の神様」と言われ、「天満宮」と言われる神社はすべて菅原道真公を祀った神社である。特に総本山と言われるのが九州の「太宰府天満宮」、京都の「北野天満宮」である。
当初は低い身分であったがずば抜けて優秀であり、宇多天皇(うだてんのう:第59代)に重用され、忠臣として力を発揮した。子供の頃から和歌を詠み、優秀さは有名だった。最も大きな功績は、当時で250年続いていた遣唐使を止め(894年)、日本のあるべき姿を模索した。後の国風文化を生むきっかけとなったと言われる。
しかし、それにより当時の実力者、藤原時平の策略により九州に左遷されることとなった。失意のその時に、読まれた和歌が以下である。
主(あるじ)なしとて 春な忘れそ
(春風が吹いたら、香りをその風に託して大宰府まで送り届けてくれ、梅の花よ。私がいないからといって春を忘れてはならないぞ)
菅原道真公はこよなく梅を愛した。梅にまつわる歌も多い。道真公は普段から梅を好み、自宅の庭に植えて大事に育てた梅を思い詠ったと言われる。菅原家の家紋は梅の花を示しているほどである。
この歌は、九州へ旅発つとき自宅の梅を見て詠われた。梅に対する思いの深さを感じずにはいられない歌である。
(2) 平安時代の歌人 紀貫之(きのつらゆき)
紀貫之(きのつらゆき)も平安の人である。道真公と年代はほぼ近い。歌人でもあり、古今和歌集の変遷を命じられ、種々の歌をよく変遷した。こよなく梅を愛した「歌人の大家」が詠んだのが、下記の和歌である。百人一首にもあるので、知っている人も多いと思う。
花ぞ昔の 香ににおいける
(人の心はどうだかは分からない。しかし慣れ親しんだこの土地では、梅の花が昔とかわらずにすばらしい香になって匂っていることだ。)
もともと「古今和歌集」にあった歌で、百人一首にも選ばれた。この歌だけでは「梅」を指しているかどうかはわからないが、背景を見るとこの歌の意味を深く理解できる。
長谷寺(奈良)へお参りするたびに泊まっていた宿に久しぶりに訪問すると、宿の主人に「昔どおりに宿はあるのに、あなたは心変わりしてしまったのですね」と言われ、紀貫之は宿の梅の枝を折って「人はいさ…」と詠んだという。
梅を通じた物の見方を示した歌として残っている。これに対する主人の返しの歌もあるので、興味のある人は是非。
(3) 幕末の異端児 高杉晋作
時代はずいぶん下って、江戸幕府の末期をみたい。
江戸幕府末期の維新の志士高杉晋作も、梅を愛する日本人であった。奇兵隊を編制し、明治維新の原動力となった長州藩を大きく導いた高杉晋作について、語り出したらきりが無い。私の最も尊敬する先人の一人である。
その高杉晋作は常に暗殺の危険と隣り合わせであった。そのため、名をいくつももっているが、その一つが「谷梅之助」である。漢文に通じていた高杉晋作は菅原道真公を尊敬しており、「谷」は道真公を祀る「天神信仰」からのものである。そして「梅」を愛していた高杉晋作が自分につけたのが「梅之助」である。
また、高杉晋作の長男は元治元年(1864年)に生まれたが、その名は「梅之進」であった。後に改名しているが、高杉晋作が如何に梅を愛していたかうかがえる。
3.愛知県の梅のスポットの一つ「大縣(おおあがた)神社」の梅祭り
ページ目次 [ 開く ]
梅をみたいと私の地元での梅のスポットを調べたら、愛知県の犬山市にある「大縣(おおあがた)神社」に出会った。有名な神社ではあるがあまりなじみがなく行ったことがなかった。梅に引かれて行ってみた。
ちょうど見頃に行ったこともあり、素晴らしい「しだれ梅」を見ることが出来た。これだけ集まった梅は、単独で咲く美しさとは少し趣が異なるが、由緒ある神社の裏に集まる梅の花は、非常に落ち着いた感じの「華美」を感じた。大変いいものなので、近い人は是非お勧めしたい。

大縣神社 梅祭り4 

大縣神社 梅祭り3 
大縣神社 梅祭り2
4.大縣(おおあがた)神社の歴史と散策
ページ目次 [ 開く ]
ついでではあるが、愛知県犬山市の大縣(おおあがた)神社について記述したい。

大縣(おおあがた)神社の創建は紀元前と言われる。御祭神は説が種々あるがはっきりしない。尾張地方にあって「尾張開拓の開祖」と言われて古代から親しまれた神社である。
大縣神社は、ひっそりとあるが、由緒正しい神社がひしめく尾張の地方にあって、堂々の「二宮」である。
「一宮・二宮・三宮」とはどのように決めたかはなかなか定まらないが、大和の時代からその地方での社格が伝わったと言われる。尾張の地にあって最も有名な「熱田神宮」は「三宮」である。なお、「一宮」は文字通り一宮市にある「真清田(ますみだ)神社」である。
それほどの社格と伝統をもつ大縣(おおあがた)神社は、山の麓(ふもと)にあるが、山頂にある「本宮」はそこから更に歩くことでいける。標識にも、「20分程度」とあったのであまり考えずに歩いてみた。

軽い気持ちで歩いたが、すぐにそれを反省した。年のせいかわからないが、ひたすら上り坂が続き、まったく「散策」というレベルで行くと裏切られる。「登山」と言うほどではないが、相当な山道コースであった。
体力にはそれなりに自信のある方だったが、ここまで疲れるとは、と本当に苦労した。何度も心が折れそうになる自分を叱咤しながら進んだ。
しかし、その結果見られた本宮とその風景は素晴らしかった。まさに「神々しい」とも言える風景と、由緒ある神社の本宮ということで更にありがたみが増し、感謝の気持ちで見られた絶景であった。
しかし、本宮に行くにはそれなりの覚悟を持つことを忘れずに。本当にきつかった・・・。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。




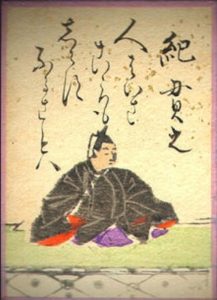












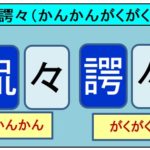





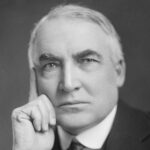


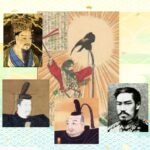

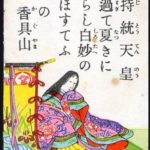


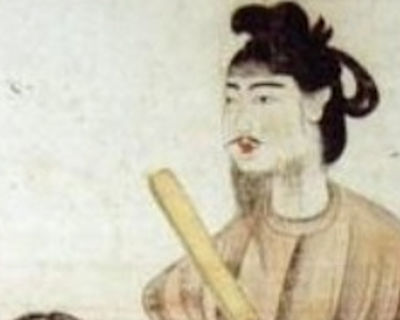
太宰府にある梅ヶ枝餅はそういうことかぁ!!菅原道真公が大好きだったからなのね。知らずに頬張ってましたわ。 てつさんが大好きな高杉晋作も梅を愛したとあれば益々魅力的だね。
しかし、散策大得意のてつさんが疲れるくらいだから、大縣神社の本宮までの道のりはよっぽどだったんだねー。大学時代の初詣はいつも大縣神社でした。久々に行ってみたくなりました。
梅の魅力はなかなかだよ。
大縣神社はほんとおすすめっす!
お疲れ様でした。いい写真ですねー!私も今度チャレンジしてみます。
梅もいいですね。先日行った湯島天満宮でも梅が咲いており、とても良い香りがしました。
梅もよかったですけど、山頂の本宮もほんと良かったです。いい写真が取れました。
ほんとにヘトヘトでしたけどね。逆にそれくらい苦労したからこそ、いい景色に感じるんですかねぇ。