
『散る桜 残る桜も 散る桜』という、良寛和尚の言葉に思う
ふと出会った言葉を取り上げたい。江戸の中期の禅宗の僧侶であった良寛(りょうかん)和尚の言葉である。非常にシンプルな言葉だがなぜか心に残った。

ふと出会った言葉が印象的だったので取り上げたい。「読んで字のごとく」の句であるが、江戸時代中期で禅宗の「曹洞宗」の僧侶だった「良寛(りょうかん)和尚」の詩である。
散る桜 残る桜も 散る桜
良寛和尚

良寛和尚の「辞世の句」と言われるこの句は、戦争の時にも使われたという。「別れの詩」とも言える。
しかしこの詩は、「生」を受けた人間・植物・動物のはかなさを簡潔に述べると同時に、限りある「生」を使ってどのように生きていくか、どのように死ぬのか、を問う詩にも読める。
なぜかこれを聞いて、印象に残った。自分の父も含め、散っていった先人達がいる中で、今の自分が「残る桜」として存在している。そして、いずれは「散る桜」としてどのように生きていくのか、自分で模索していきたい。
良寛和尚は、江戸時代中期の宝暦8年(1758年)に生まれた人である。もともとは越後国(今の新潟県)に「名主(なぬし)」の家(いわゆる「名家」)に生まれたが合わず、仏門に入り禅宗の曹洞宗にて修行する。
名家の出にもかかわらず、仏門の修行をしながら質素な生活を営み、晩年は故居に帰り、書物を書いたり句を詠んだり子供の相手をしたりして、村の人から好かれていた人だった。
「桜の国」の日本人らしい、生と死を見据えた潔い詩と思う。散ることも意識しながら、今に「残る桜」としてしっかり進んでいきたい。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。




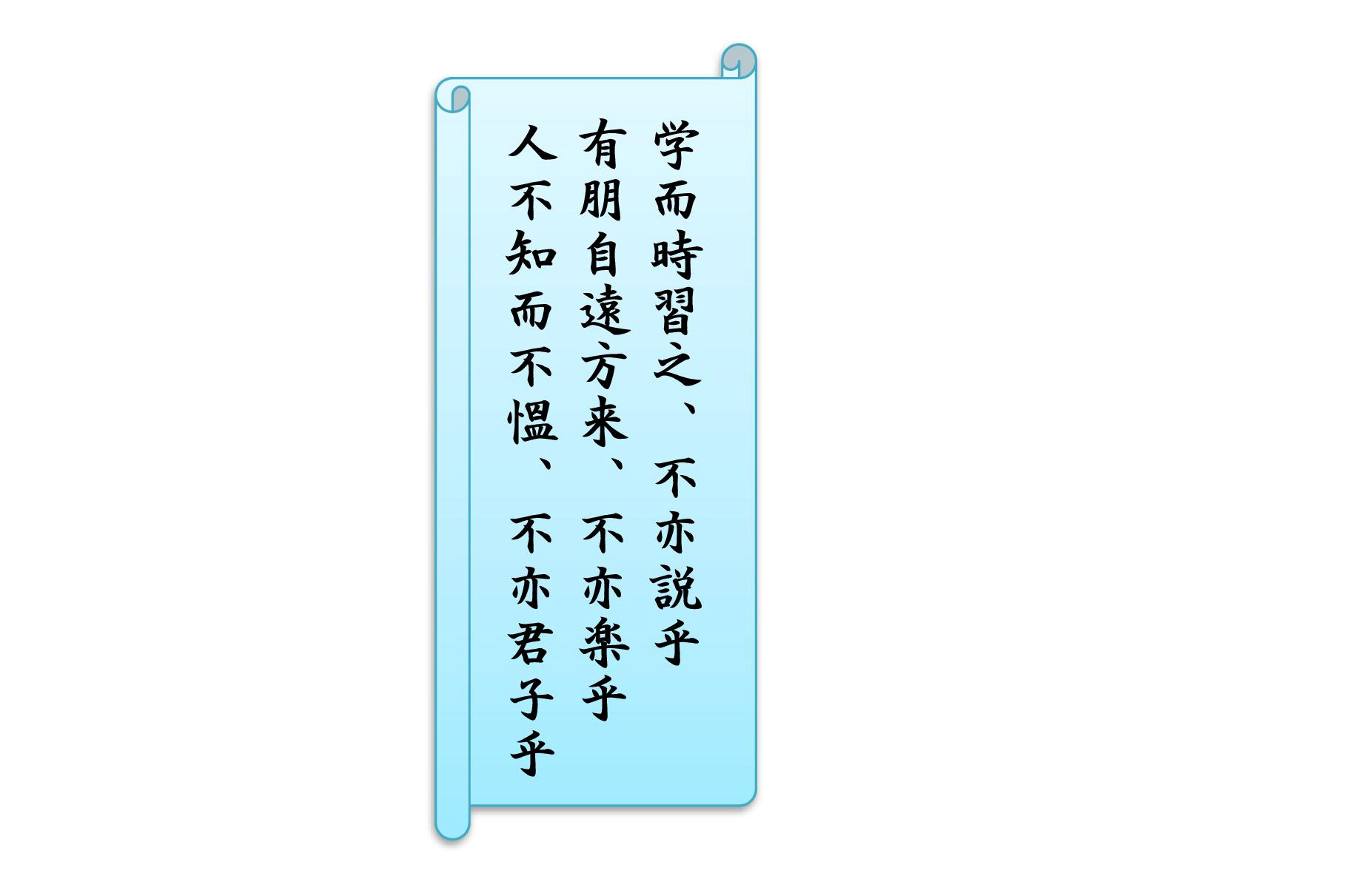













この記事へのコメントはありません。